
 最近の更新(17年4月〜)
最近の更新(17年4月〜)
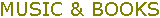
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |

 最近の更新(17年4月〜)
最近の更新(17年4月〜)
|
|
ダニエル・L・エヴェレット 『ピダハン』(みすず書房)
|
|
アマゾンの奥地にわずかに残るピダハン族のもとに、キリスト教の伝道に行った著者が、その言語と生活に魅かれ、言語学の研究者となり、一方でキリスト教の信仰を捨てて、家族とも別れる。30年以上の彼らとの生活を通じて得た知見を、言語学・人類学の研究者としての論理を通して描き出している。学者としての論文は多数であり、それは言語学・人類学のみならず多くの分野に衝撃を与え続けてきたが、はじめて書かれた一般向けの本書は、分かりやすいばかりか、初期に家族がマラリアにかかって重篤なときの、医者にたどり着くまでの冒険譚など、手に汗握る描写すらあって非常に面白い。もちろん自身も命を落としかねないことたびたびである。 ピダハン語には数詞も色名もないばかりか、左右の別もなく、過去や未来もない。これではキリスト教の布教や聖書の翻訳どころではないが、そもそもチョムスキーに代表される言語学の通説がひっくり返ってしまう。過去も未来もない言語は、そのまま彼らの生活や意識そのものなので、歴史は直接会ったことのある二世代前ぐらいまでしかないし、会ったこともない神や、将来に控える最後の審判など話は通じない。怒りを表現したり暴力を振るわない、などというと西洋的な寛容の精神と履き違えてしまいそうだが、それとはまったく異質な世界である。家族関係や性関係なども興味深いし、外の世界との軋轢にも一般の読者としてははらはらさせられ通しである。 学問的な興味はなくとも、読み終わればピダハンに生き続けてほしいという気持ちになることは間違いない。 |
|
橋場弦 『丘のうえの民主政 古代アテネの実験』(東京大学出版会)
|
| 最近、必要があって古代思想を読み直しているので、本棚をひっかきまわしている。20年前(1997年)に発行された本書、古代アテネの民主政を活き活きと描いているのだが、改めて読んで、現代の民主政治に照らし合わせて考えさせられることが多いと気付かされた。古代史の研究者である著者が、一般向けの教養書として執筆依頼を受け、書きあげただけあって、(20年たっているから学問的には古いところもあるのかもしれないが)歴史学の裏付けをもとに、目に見え手に取るように当時の民会の様子などが描き出されているから、まず読み物としてたいへん面白い。ところどころは映画にしてもよさそうだと思うほどである。私が本書を読み直した直接の理由は、ソクラテス裁判の解釈に関する記述があったはずだと思い出したからなのだが、ペロポネソス戦争の敗戦後の三十人政権による民主制の破壊とその後の再生という歴史的背景は、読み直してみるとそれ以上の、今の日本の政治状況と照らし合わせてみて示唆されるところが多い。民主主義の危機とはどういうことで、そこからの脱却は可能なのか、いささか重い気持ちで考えさせられることになった。 |
|
大塚ひかり 『女系図でみる驚きの日本史』(新潮選書)
|
|
政治や教育で「日本の伝統」を言う人たちのうさんくささにはいつも辟易しているが、夫婦別姓や女性天皇への反対や父権復活あたりに非常に情緒的(であることをごまかすための都合のよい論理のでっちあげになってくるとインテリジェントデザイン論なみに宗教的)な言説には、そもそもあなたのいう「日本の伝統」はどこから?鼻から?喉から?とでも茶化してみたくなる。 もちろん本書の著者には私のような質の低い関心はない。日本古典文学オタクから道を究めるのに必然的に家系図を書くようになった著者は、まさに必然的に女系図の面白さに行きつくのである。「平家は滅亡していない」という帯の文句のように、言われてみればそうか!というばかりか、外戚の権力排除から徳川将軍家の女系図の不在まで、いろいろな謎がするすると解けてくるから、歴史に弱い私にだってこれはたまらない面白さである。タイトルに「驚き」なんて付けるのは陳腐だと思いがちだが、本当に日本史の見方が劇的に変わる驚きを味わうことができる。女系図を手繰ることは、イブ原則やミトコンドリアDNAなどの生物界の姿が映しあわされもして、つながりあって新しい見え方が立ち現われてくる。 |
|
NHKスペシャル取材班 『縮小ニッポンの衝撃』(講談社現代新書)
|
| 少子高齢化対策こそ名ばかり政策の最たるもののように思うのだが、それというのも少子高齢化対策にはタブーが多すぎるからであると思う。むしろ人口が減少したほうが良いことはたくさんあって、政府はのらりくらりしながらそれを待っているのではないかと思うし、労働者不足も年金不足も、実際にそうなってしまったらそれでやるしかないじゃん、と居直って済ませようとしているのだろうと思う。どのような政策もたいがいはその場しのぎにすらなっていなくて、やってますよという言い訳程度のものばかりだ。簡単に言えば子供を生んだ方がもうかる仕組みにするほかにないのだが、そのためには税配分から家族意識から、変えなくてはならない物事が多すぎて、まあたぶんやる気はないだろう。16万件余りの人工妊娠中絶数は、ついに100万人を切った出生数を埋め合わせるには足りないものの、その背後にある膨大な避妊を考えれば、「(経済的に)安心して子供が産める社会」の実現は最低条件である。 |
|
パオロ・マッツァリアーノ 『みんなの道徳解体新書』(ちくまプリマー新書)
|
| 偽イタリア人マッツァリアーノ先生の道徳教育批判。いちいちごもっとも過ぎて、これを読むと(いや本当は読むまでもなく)、いったい何でこんなことになってしまったのだろうと、あっけに取られるしかない状況になっている。ついに教科「道徳」の実施が目前に迫り、教科書検定が進んでいるところであり、学校教育全体で見れば私の専門である高校『倫理』は、新設『公共』の必履修化に伴い完全な選択科目になってしまう(現行では『現代社会』の代わりに『倫理』+『政治・経済』を置くことができたが、それがなくなってしまう)。こうした一連の変化が何を意味するかは明らかであろう。学校教育は「ちゃんと考える人」ではなく「言うことをきく人」を作れ、という、あからさまなメッセージである。 とはいえ、そんなに簡単に「言うことをきく人」を学校が作れるわけがない(そんなことができるのなら学校は楽なもの)。退屈でわけのわからない、しかし敏い子どもは忖度し、鈍い子どもはそっぽを向くような、「道徳」の時間が毎週ムダに過ぎていくのであろう。 現代の日本、実際には、統計的には明らかに治安は向上し、少年少女の犯罪は減って、テレビ番組もすっかりお行儀がよくなってしまい、ネット上には息苦しいほどの道徳的な批判があふれている。なのになぜ、教科「道徳」なのか。少年少女に「ズルしちゃいけない」と叩き込めという人たちは、自分たちだけがズルしていられるようにしたいのである。トリクルダウンやらいわゆるモリカケやら、ここ数年来の政財界の言辞を振り返るまでもなく、臆面もなく「ズルしちゃいけない」という人たちの、ズルさ醜さは目も当てられない。本書に取り上げられている副読本の例でいえば、雨のバス停の話はまさにそれだ。 いまや、過去を根拠無く美化して、ズルしたい人=自分たちの天国にしたいという目論見をまんまと果たさせてしまった。高度成長期の日本は本当に汚かったし、戦前はもっとひどかった。そして、「なぜ人を殺してはいけないのか?」と問う若者を叩く大人たちは、じつのところ「自分が納得できる理由があれば、人を殺してもいい」と考えている。死刑や戦争を理屈付けで容認する以上、そう考えていることは明らかなのに、いのちの大切さなどというあたりまえの話でお茶を濁してきた。本当に教えなければならないことは何か。著者の主張は明らかであり、ここまで読んできて少しの違和感を引きずっていたとすれば、それが解決するカタルシスでもある。 本書は著者名のいかがわしさにひるむことなく、ぜひ広く読まれるべき本である。昔から今までの「修身」教科書や「道徳」副読本の傑作な事例(もちろん、中には良い物もあるのだ)多数。それだけでも楽しめる(気分は重くなるが)。 |
|
安田登 『身体感覚で「論語」を読み直す。古代中国の文字から』(春秋社)
|
| 孔子と『論語』について頼まれた原稿が一向に進まない。頼まれて書く以上は、よりよいものにしたいのは当然で、かといって私の専門ではないから論文を読みこんできたわけもなく、とりあえずは出版されているものに目を通して、と始めたら、もうきりがないのである・・・というようなことはこれまでも書いてきた。そしてどうも、この本は、できれば知らずに済ませておきたかった本かもしれない。著者は能楽師であり(大学では中国思想を学んでいる)、題名にあるように研ぎ澄まされた身体感覚の持ち主でもあるから、その点は覚悟して読み始めた。しかしもう一つの「古代中国の文字から」ということが、特に衝撃的なのである。なにせ、「四十にして惑わず」の「惑」という字は、孔子の時代にはなかったというのだから。そもそも、「心」という字が出現してから500年ほどしかたっておらず、「心」を部首にする文字も現在よりはるかに少なかった。いいかえれば、「心」が発見されてまだ間もない時期に孔子は活躍した。それを前提にして読まないと、『論語』が分からないのではないかということになる。先の「惑」であれば、音と旁から考えて「或」であったのではないか、そうすると、四十歳は「惑わなくなる」のではなくて「或(かぎ)らない」、つまり自分はここまでだ、と限界や範囲を決めつけないで、広げていく歳だということになるから、だいぶ意味は変わってくるわけである。本書は多くの事例を取り上げて、『論語』の解釈を豊かにするのみならず、孔子という人物の位置づけを大きく変える可能性を示している。うーんこれでまた書き直さなくてはならなくなる・・・。 |
|
最相葉月 『れる られる』(岩波書店)
|
| 自分が生きている現実の「境目」が見えるとき、つまり自分の現実の「向こう側」に気づくとき、それは恐ろしさなどという言葉ではとうてい表現しきれない、存在の不安に突き動かされるのだが、本書は6つの章でそれぞれの「境目」に立つときの生々しい呆然さがたんたんとえがかれている。著者の経験に結び付いていて、精神をすり減らし、肉体を切り刻むような痛みと絶望が漂っている。生まれてくること、災害に立ち会うこと、狂わされること、愛されること、、、。これらの言葉に触れることは、私はなぜ今ここでこのように生きていられるのかを自問することでもある。 |
| 内藤正典 『となりのイスラム』(ミシマ社) |
|
長年担当してきた、江戸東京の宗教を考える夏期集中講義も、カリキュラムの変更で今年限りとなった。この講義はほとんどが宗教施設の訪問見学で、その日も見学コースの東京ジャーミイに行ったら、おそらく近くのインターナショナルスクールの子供たちだろうか、十人ほどで礼拝にやってきた。一年生くらいの女の子たちが、モスクに入るや否や絨毯にごろんとひっくり返っては楽しそうに笑い合っている。子どもたちの無邪気なふるまいは、寺でも教会でもモスクでも変わらず、愛らしい。やがて先生が彼らをまとめて、礼拝が始まった。もちろん、もうふざけている子はいない。 いまや街中でムスリムの人たちと出会うことはごく当たり前のことになったし、近所や友人にもいるから、昔とはだいぶ変わってきたが、ムスリムの暮らし、日常感覚が理解できているかというと心もとない。礼拝にやってきた可愛い子どもたちが絨毯に寝転んでしまうんだなあ、というような小さなことも驚きである。 本書は、親しみやすいタイトルと装丁で、著者が研究してきたイスラームについての目配りの利いた、優しい語り口の入門書になっているが、内容はなかなか深く、現在のISのテロなども論じていて、単に異文化交流で仲良くしましょうというような話ではない。年に一度はトルコの家で暮らしていて、ムスリムの生活について私たちが知らなかったことが良く分かるというだけでなく、ISがなぜ存在し、どこに問題の本質があるかについて、考えさせられる。ムスリムがISのテロを否定するのは、現代のイスラームが西洋の影響を受けているからではなく、イスラームの歴史の中で培われてきた精神に反するからだということを、とても丁寧に説明している。 分かりやすいから価値があるのではなく、考えさせられるから価値のある本だと思う。 |
| 森達也 『放送禁止歌』(光文社知恵の森文庫) |
|
初版2000年、文庫版2003年と、もう17年も前の本なのだが、今改めて読むべき一冊かもしれない。結論は先の方に書かれているからあえて言ってしまえば、いわゆる「放送禁止歌」なんてものはない。民放連のガイドライン的なリストは1983年を最後に更新されていないし、いわゆる「放送禁止歌」として知られている『イムジン河』や『手紙』や『自衛隊に入ろう』などは、そもそもそのリストにも入っていない。つまり、あるのは「自主規制」のみである。テレビ局は「抗議がくるから」という口実で、実際にはその抗議すら来ていないのに自主規制する。 今日ではすぐにネットが炎上し、メディアも異様なほどそれに気を遣っている(ように見える)。ネットニュースのコメントを見れば、そのほとんどは匿名を使った言いっぱなしの腹いせである。ネット時代になるまではその場限りの「酒場談義」だった。私はmixiがニュースを配信するようになって、それに付くコメントがあまりにもつまらなくて不愉快なので、コメントを表示させないようにできないかと意見を伝えたことがあったが、状況はさらに悪化して、ヤフーニュースのコメント欄などはほんとうにひどい。そういうコメントを(あまり見たくないのだがあえて)見ると、自分が「世間」の代表になっているかのような、自我インフレーションを起こしていて、これに過剰に反応するメディアが自主規制するというのは、ただの(しかし深刻な)悪循環である。この悪循環は、メディアの側が断ち切る必要があると思うのだが、日本のテレビ局の実態、スポンサーや芸能プロとの長年の関係から、巧妙に対応することができないのだろう。 森達也はあえて『放送禁止歌』をテレビのドキュメンタリー番組として制作し、そこから自主規制の深刻な状況を、自らが身を置く業界の内側から見いだしていく事になった。そのプロセスを見て、さらに楽観ではないかもしれないが光を見いだしているかのような文庫版のあとがきを見ると、ネットの普及で17年後の現状がむしろ悪くなってきていることに、読み手としては暗澹とするほかはない。 |
| 清水真木 『新・風景論』(筑摩書房) |
| 私は給水塔が好きなのだが、給水塔単独はもちろん、給水塔のある風景も楽しみの一つで、低層の住宅街の中に屹立する巨大な配水塔や、人気の少ない山の中に鮮やかな色と形で圧倒する工業用水の配水塔など、見に行っては写真を撮ってきた。しかし、街中の、特に団地の給水塔を撮りに行く時、しばしば電線に悩まされた。よいアングルだと思っても電線が入り乱れて映り込む。電線地中化はぜひ推進してほしいと思ってきた。ところが最近、電線を愛好する人たちがいることを知った。彼らは、電線地中化に反対していて、それを知って以来、電柱や電線の見方、というより見え方が変わった。本書は日本橋と首都高について論じることが導入になっているが、私自身の体験から大いに共感させられることになった。もともと著者の風景論についての講演を3年ほど前に聴講して、興味深く思っていたが、その時のポイントは「風景」よりも「風景画」が先に在ったという、コペルニクス的転回風の気づきであった。本書は、その後の研究の深まりを感じさせつつ、読みやすい文体で、知らなかったことや新しい見方がたくさん出てきて、学術的なのに誰が読んでも楽しめると思う。 |
| 野崎まど、大森望編 『誤解するカド』(ハヤカワ文庫JA) |
| ファーストコンタクトSF短編の傑作選として、日本・海外合わせて10篇がセレクトされている。JA番号なのは、野崎まど脚本による『正解するカド』というアニメの公開にちなんでのアンソロジーだからである。これを買った理由は唯一つ、巻頭が筒井康隆『関節話法』だったことで、これは昔、筒井の短編集で読んで「腹が捩れるほど」笑ったので、もう一度挑戦しようと思ったのだ。買って電車の中で読んで、やっぱり笑いをこらえるのに必死だった。セレクションは非常に個性的で、古典的な海外物にコニーウィリスが混ざっていたり、お笑いから難解なもの、問題作まで、まあいろいろ。最後まで読んでいまひとつ、コンセプトがつかめなかった。自分の好みとしてはやはり筒井以外は海外物になる。ところで、「関節」と「間接」よりもよくやらかす変換ミスに「内臓」と「内蔵」があるが、これに引っかけた短編はないかなと探してみたら、小説は見つからなかったけど、10年以上前のこんなエイプリルフールネタが残っていた。小説を誰か書いていないだろうか。 |
| 影山輝國 『「論語」と孔子の生涯』(中公選書) |
| 『論語』モノ、孔子モノの本は書店に行ってもあふれていて、玉石混交も良いところだが、本書はあまりにも地味な装丁やタイトルのために埋もれがちながら、たいへん面白い一冊なのである。『論語』の古注・新注の紹介からはじまって、これもなるほどと思わせるのだが、影山先生は『論語義疏』の紹介に入り、その面白さをいきいきと伝え始めるのである。『論語』書き出しの「学びて時にこれを習う」の解釈も、別説として学者の一生を述べたものとする解釈を紹介し、三番目の段落を人に教える立場になったところとして、自分の教えを理解しない人がいても怒ってはいけない、という解釈があるのである。なるほど面白いが、ここで影山先生は「私はこの解釈を知ってから、学生に対して決して怒らなくなった。以前はたいへん厳しく指導し、「鬼の影山」と怖がられていたが、いまでは「仏の影山」に変身し、学生に愛される存在になった。これも『論語義疏』のおかげと言えようか。」(p.17)ね、面白いでしょ。こういう、ちょっとした面白い先生本人が顔を出す。もちろん、研究に基づいた知見がちりばめられているのは当然と言うかそれが中心なのだが、軽快な筆致の「コラム」が挟み込まれていたり、構成も読者サービスにあふれている。学術的な内容に、著者の皮肉の効いたいたずら精神が時折顔を出す、類書のない面白さ。オーソドックスな注釈の岩波文庫本などを読み終えたら、次によく『論語』や孔子を知るための一冊として、本書はまことに優れている。2016年に発行。これからの『論語』読みには欠かせない一冊である。 |

